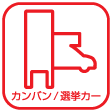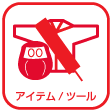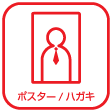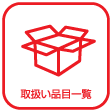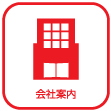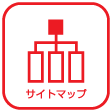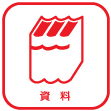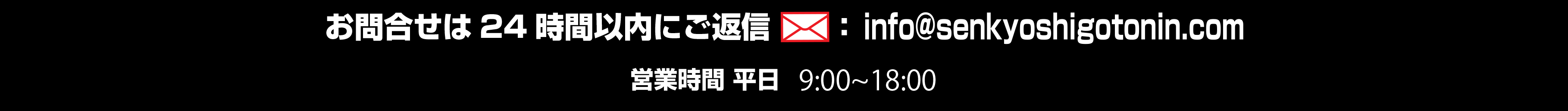選挙ポスターから選挙看板,選挙カーまで選挙専門の制作会社 選挙に勝ち抜く為のツールを考える選挙仕事人
選挙ポスターから選挙看板,選挙カーまで選挙専門の制作会社 選挙に勝ち抜く為のツールを考える選挙仕事人
選挙の供託金没収ラインとは?各選挙ごとの条件と返還基準を詳しく解説
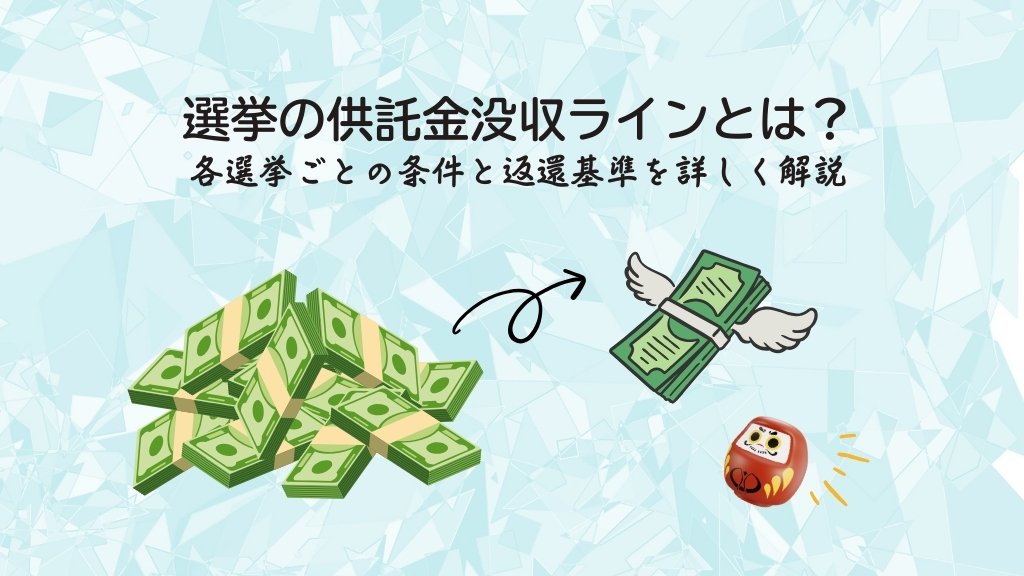 選挙において必ず行わなければならない手続きのひとつに、「供託」があります。
選挙において必ず行わなければならない手続きのひとつに、「供託」があります。
供託を行うにはまとまった資金が必要となりますので、供託金は選挙における必要経費と捉えることができます。もし立候補を考えている方は、供託制度についてしっかりと理解しておきましょう。
供託の基本的なルールと、どのような場合に供託金が戻ってくるのかについて、これから説明いたします。
供託金の没収ラインとは?選挙での基本的な仕組みを解説
◎供託金の仕組みとは?どの選挙でも必要になるの?
「供託」とは、一定額の現金や国債証書を法務局に預けることです。
すべての選挙において、立候補手続きを進める際には、供託を済ませたことを証明する書面が必要となります。
要するに、供託金を用意することができなければ、選挙に立候補することはできません。
選挙の制度上、なぜ立候補に供託が必要とされているのかというと、一定の資金を候補者に用意させることによって、むやみに立候補者が乱立することを防ぐためです。選挙は多くの人々の民意を議会の場に反映させ、民主主義の根幹を成す大変重要なものです。
選挙を実施するにあたっては混乱が起きないことや、公平性が保たれることが求められているのです。
供託金の金額は、選挙の規模などに応じて定められています。一般的には、選挙の規模が大きくなればなるほど、供託の金額も多額となります。
たとえば、選挙の規模が大きい衆議院議員(小選挙区)・参議院(選挙区)・都道府県知事であれば300万円が必要です。
一方、選挙の規模が小さなものとしては、町村長であれば50万円、町村議会議員であれば15万円が必要となります(公職選挙法第92条・93条)。
◎選挙で供託金が没収される条件は?
選挙の結果を受けて、得票数がある一定の割合に達しなかった場合には、事前に法務局に預けた供託金が返還されることはありません。
さらに、途中で立候補を辞退したり、とりやめた場合などにも、同様に供託金は没収されてしまいます。
供託金はそのまま没収されることになるのです。没収された供託金は国政選挙であれば国庫に納められ、地方選挙であればそれぞれの地方自治体に納められて、他の税金と同じように扱われることになります。
供託金が没収される基準:各選挙ごとの違い
供託金が没収されてしまうボーダーラインは、選挙ごとに変わってきます。
選挙の種類と供託金が没収される得票数は、以下にまとめてあります。
該当する選挙に求められる得票数を確認してみましょう。
<選挙の種類と供託が没収される得票数など>
| 選挙の種類 | 供託物が没収される得票数・没収額 |
|---|---|
| 衆議院(小選挙区) | 有効投票総数×1/10未満 |
| 衆議院(比例代表) | 没収額=供託金-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) |
| 参議院(選挙区) | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満 |
| 参議院(比例代表) | 没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2 |
| 都道府県知事 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 都道府県議会 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
| 政令指定都市の長 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 政令指定都市議会 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
| その他の市区の長 | 有効投票総数×1/10未満 |
| その他の市区の議会 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
| 町村長 | 有効投票総数×1/10未満 |
| 町村議会 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満 |
供託金の返還条件:得票率が一定ラインを超えた場合、返還される!
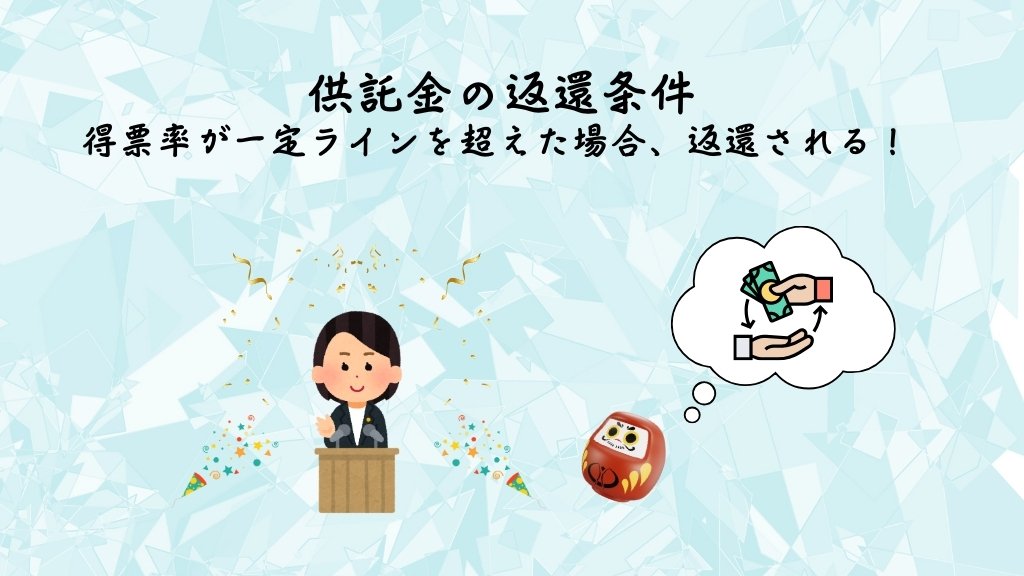
選挙において一定の得票数以上を得ることができれば、法務局へ預けた供託金は候補者へと返還されます。
また、選挙においては立候補する人数が当選定数を下回ることも想定されます。
たとえば、過疎地での選挙などでは、市町村議会などで定められた議員の人数よりも、立候補手続きを行った人数の方が少ないことで、選挙そのものが行われることなく無投票当選となります。無投票当選の場合にも、供託金は返還されることになります。
供託金が返還されるタイミングは、選挙における得票数が確定し、選挙管理委員会から証明書が送付された後です。
法務局にて、得票数の証明書を添えて、供託金返還に関する所定の申請書を提出しましょう。
一般的には銀行口座への振り込みという形で、供託金の返還が行われます。手続き完了後、約数週間程度で供託金と同金額が振り込まれます。
供託金没収ラインの選挙や候補者への影響と改善の余地
供託金の没収制度が定められていることは、どのような影響を与えているでしょうか。
まず、供託はかなりまとまった金額が必要であることから、資金力のある資産家の方が選挙に立候補しやすく、政治に対する志や能力があったとしても、資金力が無ければ選挙への立候補が難しくなります。
また、平均的に資金力に余裕のない若者世代が、選挙に立候補しにくいという現実があります。
次に、候補者の選挙への真剣度を試すともいえる供託制度ですが、供託金が没収されることをあえて分かったうえで、売名行為や広告・宣伝のために選挙へ立候補するようなケースが見受けられるようになりました。
たとえば、2024年夏に実施された東京都知事選挙においては、供託金の没収対象者が53名にものぼり、供託金没収の総額は1億5900万円にものぼったといわれています。
遊び半分で選挙に立候補するようなことがあることは許されませんが、選挙における供託制度そのものにも改善のための議論の余地はあるのかもしれません。
選挙仕事人 お問い合わせはこちら

選挙仕事人では、選挙ポスター、選挙看板、選挙タスキ、選挙カー、スピーカー音響セットなど、選挙に必要なツールを幅広くご提供しています。必要なものがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
また、ご要望に応じて、公職選挙法の範囲内でオリジナル製作も承ります。皆様の選挙活動を全力でサポートし、誠心誠意対応させていただきます。
候補者の皆様からのご依頼を、心よりお待ちしております。
メール:info@senkyoshigotonin.com
ホームページからのお問い合わせ:https://www.senkyoshigotonin.com/toiawase.html
※メールでのお問い合わせには、24時間以内にご返信いたします。
年中無休で対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
まとめ
このように、供託は選挙において非常に重要な手続きのひとつです。
供託金の準備が出来ずに立候補ができなかったというようなことがないように、立候補を予定している方は、しっかりと供託に向けた準備を進めておきましょう。
もし何か分からないことがあれば、立候補を予定している地域を管轄する選挙管理委員会または法務局へ確認してみましょう。
参考リンク
総務省-立候補を目指す方へ
時事ドットコム-供託金【選挙ミニ事典】
朝日新聞デジタル-「落選なら借金まみれ」供託金のハードル 参院選、神奈川は半数没収 [神奈川県]
島根県大田市公式サイト-供託金について