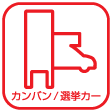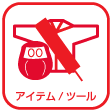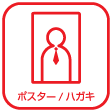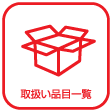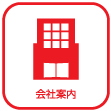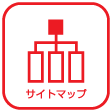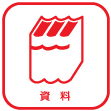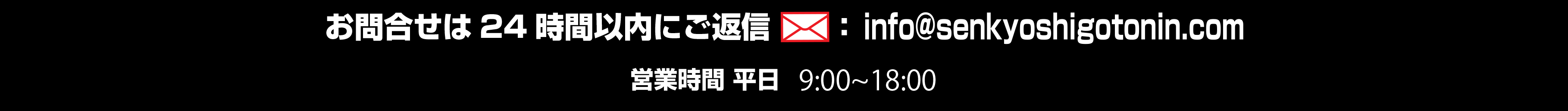選挙ポスターから選挙看板,選挙カーまで選挙専門の制作会社 選挙に勝ち抜く為のツールを考える選挙仕事人
選挙ポスターから選挙看板,選挙カーまで選挙専門の制作会社 選挙に勝ち抜く為のツールを考える選挙仕事人
選挙費用は自腹?いくらかかるのか総額や制度を解説
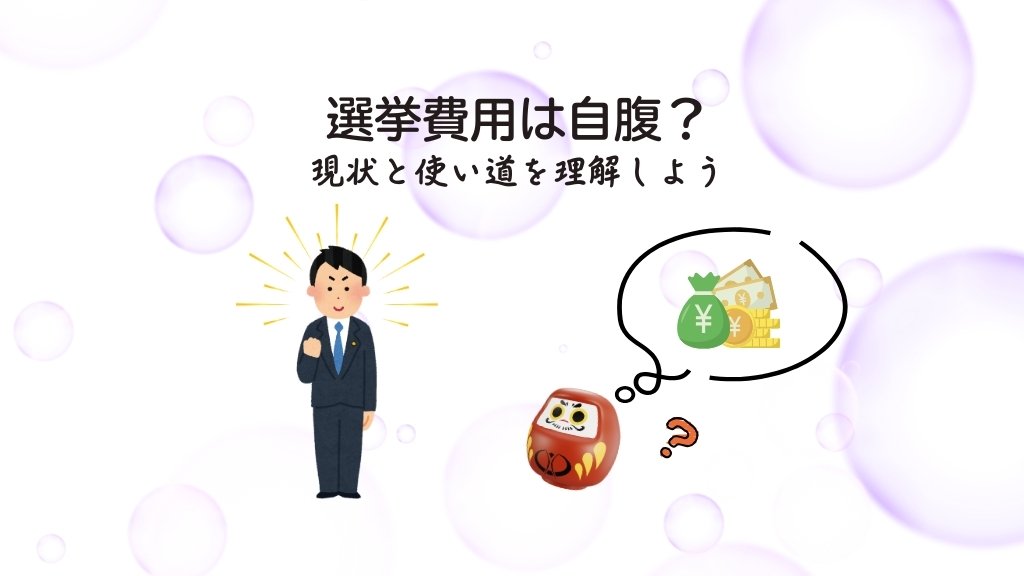
選挙に立候補するには多額の費用がかかります。供託金、選挙運動費用、そして様々な準備費用など、その総額は選挙の種類によって大きく異なります。本記事では、選挙にかかる費用の内訳や公費負担制度について詳しく解説し、立候補を考えている方々の疑問に答えていきます。
選挙にかかる費用とは?その種類と総額を把握する
選挙に立候補するには、様々な費用が必要となります。これらの費用は、初めて立候補を考える方にとって大きな不安要素となるでしょう。ここでは、主な費用項目とその概算、そして公費負担制度についてご紹介します。
◎供託金:いくら必要で、没収ラインはどこ?
供託金は立候補時に必要な重要な費用の一つです。公職選挙法第92条に基づき、選挙の種類によって金額が異なります。例えば、衆議院小選挙区選出議員選挙では300万円、市長選挙では100万円が必要となります。
没収ラインは、公職選挙法第93条に基づき、有効投票総数を議員定数で割った数の10分の1以上です。この得票数に達しない場合、供託金は返還されません。つまり、一定以上の支持を得られなければ、供託金が没収されるリスクがあるのです。
◎選挙に必要なその他の費用:何にどれくらいかかる?
選挙運動には供託金以外にも多くの費用がかかります。公職選挙法第141条に基づく公費負担制度がありますが、全ての費用をカバーするわけではありません。主な項目と概算は以下の通りです。
- ポスター作成費:約100万円
- 選挙運動用自動車費用:約100万円
- ビラ印刷費:約7万円
- 交通費:約20万円
- 写真撮影代:約5万円
これらに加えて、選挙事務所の賃借料やスタッフの人件費なども必要です。総額は、得票率によって大きく変わり、500万円から800万円程度になることもあります。
公費負担制度により、一部の費用は軽減されます。例えば、選挙運動用自動車の使用については、1日あたり最大64,500円まで公費負担の対象となります。ただし、これには制限があり、1日1台までとされています。
ポスター作成費用も公費負担の対象となりますが、作成単価及び作成枚数にそれぞれ限度が定められています。例えば、町議会議員選挙の場合、1枚あたり7円73銭、最大1,600枚までが公費負担の対象となります。
選挙運動用ビラの作成についても同様に公費負担制度があります。町議会議員選挙の場合、1,600枚まで公費負担の対象となり、町長選挙では5,000枚まで対象となります。
しかし、公費負担制度を利用するためには、供託金没収点以上の得票を得る必要があります。つまり、一定以上の支持を得られなければ、全ての費用が自己負担となってしまうのです。
選挙費用の総額は、選挙の種類や規模によって大きく異なります。公職選挙法第194条に基づき、選挙運動費用には制限があります。例えば、衆議院小選挙区選出議員選挙の場合、「名簿登録者数×15円に1910万円を加えた金額」が上限となります。
公費負担制度の現状とその限界
選挙費用は立候補者にとって大きな負担となりますが、公費負担制度によってその一部が軽減されています。
しかし、この制度にも限界があり、多くの候補者が自己負担を強いられているのが現状です。ここでは、公費負担制度の仕組みと、なぜ自己負担が避けられないのかを詳しく解説します。
◎選挙費用の公費負担制度とは?仕組みをわかりやすく解説
公費負担制度は、選挙の公平性を保つために設けられた重要な仕組みです。公職選挙法第141条に基づき、この制度により、候補者の資産の多寡に関わらず、立候補や選挙運動の機会均等を図ることを目的としています。
主な公費負担の対象項目は以下の通りです。
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用ビラの作成
例えば、選挙運動用自動車の場合、1日あたり最大64,500円まで公費負担の対象となります。ただし、これには制限があり、1日1台までとされています。
ポスター作成費用も公費負担の対象となりますが、1枚あたりの限度額が設定されています。市議会議員選挙の場合、1枚あたり3,292円が上限となっています。
重要なのは、この制度は供託金没収点以上の得票がなければ適用されないという点です。公職選挙法第93条に基づき、供託金没収点は有効投票総数の10分の1以上とされています。つまり、一定以上の支持を得られなければ、全ての費用が自己負担となってしまうのです。
◎公費負担だけでは足りない理由:自己負担の現実
公費負担制度は選挙費用の一部を軽減しますが、実際の選挙運動費用を全てカバーするには不十分です。例えば、2024年の東京都知事選挙では、公費負担を受けてもなお500万円から800万円程度の自己負担が必要となる見込みです。
この自己負担の大きさは、特に無所属や新人の候補者にとって大きな障壁となっています。政党の支援がない場合、個人で全ての費用を賄わなければならず、資金力の差が選挙結果に影響を与える可能性があります。
自己負担が発生する主な理由としては以下が挙げられます。
- 公費負担には上限があり、実際の費用がそれを上回ることが多い
- 公費負担の対象外の費用が多く存在する(例:選挙事務所の賃借料、スタッフの人件費など)
- 供託金が返還されない可能性がある
これらの要因により、多くの候補者が相当額の自己負担を強いられているのが現状です。
公費負担制度は、選挙の公平性を保つ上で重要な役割を果たしていますが、完全に自己負担をなくすまでには至っていません。特に、衆議院議員選挙や都知事選挙などの大規模な選挙では、公費負担の限度額を大きく超える費用が必要となることがあります。
また、市議会議員選挙などの地方選挙でも、公費負担制度はありますが、その範囲は限定的です。例えば、選挙運動用ビラの作成費用は、市長選挙では公費負担の対象となりますが、市議会議員選挙では対象外となる場合があります。
このような状況下で、候補者は効率的な選挙運動を行いつつ、自己負担を最小限に抑える工夫が求められます。
なぜ選挙費用はこんなに高いのか?背景を知る
選挙費用が高額になる背景には、様々な要因が絡み合っています。立候補を考えている方にとって、これらの要因を理解することは、効果的な選挙戦略を立てる上で非常に重要です。
◎選挙費用が高額になる理由:法律と運用の現実
選挙費用が高額になる主な理由として、以下の点が挙げられます。
- 広範囲への周知の必要性:有権者に自身の政策や人柄を知ってもらうため、広範囲にわたる宣伝活動が必要となります。
- 短期間での集中的な活動:公職選挙法第129条に基づき、選挙期間が限られているため、短期間で集中的に活動を行う必要があり、これが費用の増大につながります。
- 法律による制限と要求:公職選挙法は、選挙の公平性を保つために様々な規制を設けていますが、同時にそれが費用増大の一因にもなっています。例えば、第143条に基づくポスターの規格や掲示場所の制限により、効率的な宣伝が難しくなっています。
- インフレーションによる物価上昇:時代とともに物価が上昇し、印刷費や人件費などの基本的な経費が増加しています。
これらの要因が複合的に作用し、選挙費用の高騰を招いています。特に、公職選挙法の規制は、選挙の公平性を保つ一方で、候補者に大きな経済的負担を強いる結果となっています。
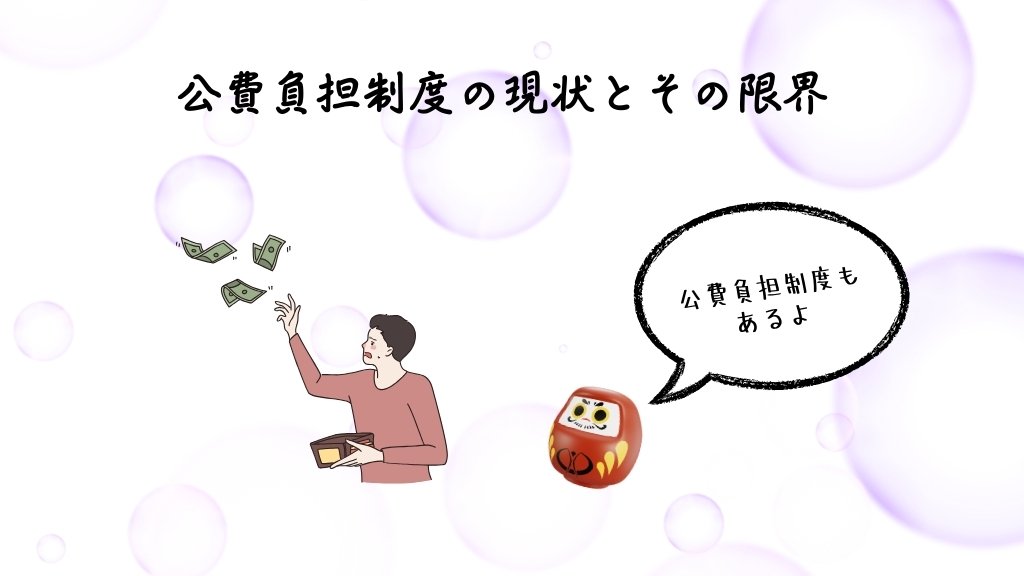 ◎国政選挙(衆議院など)と地方選挙(都知事・市議会など)の費用の違い
◎国政選挙(衆議院など)と地方選挙(都知事・市議会など)の費用の違い
国政選挙と地方選挙では、選挙区の規模や有権者数の違いから、必要な費用に大きな差があります。一般的に、国政選挙の方が地方選挙よりも高額な費用がかかる傾向にあります。
公職選挙法第194条に基づき、選挙運動費用には制限が設けられています。例えば、衆議院議員選挙(小選挙区)の場合、選挙運動費用の制限額は「名簿登録者数×15円 + 1910万円」と定められています。一方、市議会議員選挙の場合は「名簿登録者数÷定数×501円 + 220万円」となっています。
また、公職選挙法第92条に基づく供託金の額にも大きな差があります。衆議院議員選挙の場合、供託金は300万円ですが、市議会議員選挙では30万円となっています。この供託金の差も、選挙費用の総額に影響を与える要因の一つです。
選挙費用の高騰は、特に無所属や新人候補者にとって大きな障壁となっています。政党の支援がない場合、個人で全ての費用を賄わなければならず、資金力の差が選挙結果に影響を与える可能性があります。
このような状況を踏まえ、選挙費用を抑えるためには、効率的な選挙戦略が不可欠です。例えば、公職選挙法第142条の3に基づくインターネットを活用した選挙運動や、ボランティアスタッフの活用など、低コストで効果的な方法を検討することが重要です。
また、公職選挙法第141条に基づく公費負担制度を最大限に活用することも、自己負担を抑える上で重要です。ポスター作成費や選挙運動用自動車の使用など、一部の費用は公費で賄うことができます。
選挙仕事人 お問い合わせはこちら

選挙仕事人では、選挙ポスター、選挙看板、選挙タスキ、選挙カー、スピーカー音響セットなど、選挙に必要なツールを幅広くご提供しています。必要なものがございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
また、ご要望に応じて、公職選挙法の範囲内でオリジナル製作も承ります。皆様の選挙活動を全力でサポートし、誠心誠意対応させていただきます。
候補者の皆様からのご依頼を、心よりお待ちしております。
メール:info@senkyoshigotonin.com
ホームページからのお問い合わせ:https://www.senkyoshigotonin.com/toiawase.html
※メールでのお問い合わせには、24時間以内にご返信いたします。
年中無休で対応しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
まとめ
選挙費用は、供託金から選挙運動費用まで多岐にわたり、その総額は数百万円から数千万円に及ぶ場合があります。
公費負担制度はあるものの、自己負担の部分も大きく、特に無所属や新人候補者にとっては大きな障壁となっています。選挙の公平性を保ちつつ、より多様な人材が立候補できるよう、選挙制度の更なる改善が求められています。
参考リンク
愛知県選挙管理委員会事務局-候補者と選挙運動
文化放送-「選挙はお金がかかる」実際の金額を聞くと驚く?
総務省・文部科学省-私たちが拓く日本の未来 有権者として求められる力を身に付けるために-PDF
総務省-選挙公営
延岡市-選挙管理委員会事務局-選挙運動費用っていくら?
大淀町-選挙運動費用の公費負担制度について